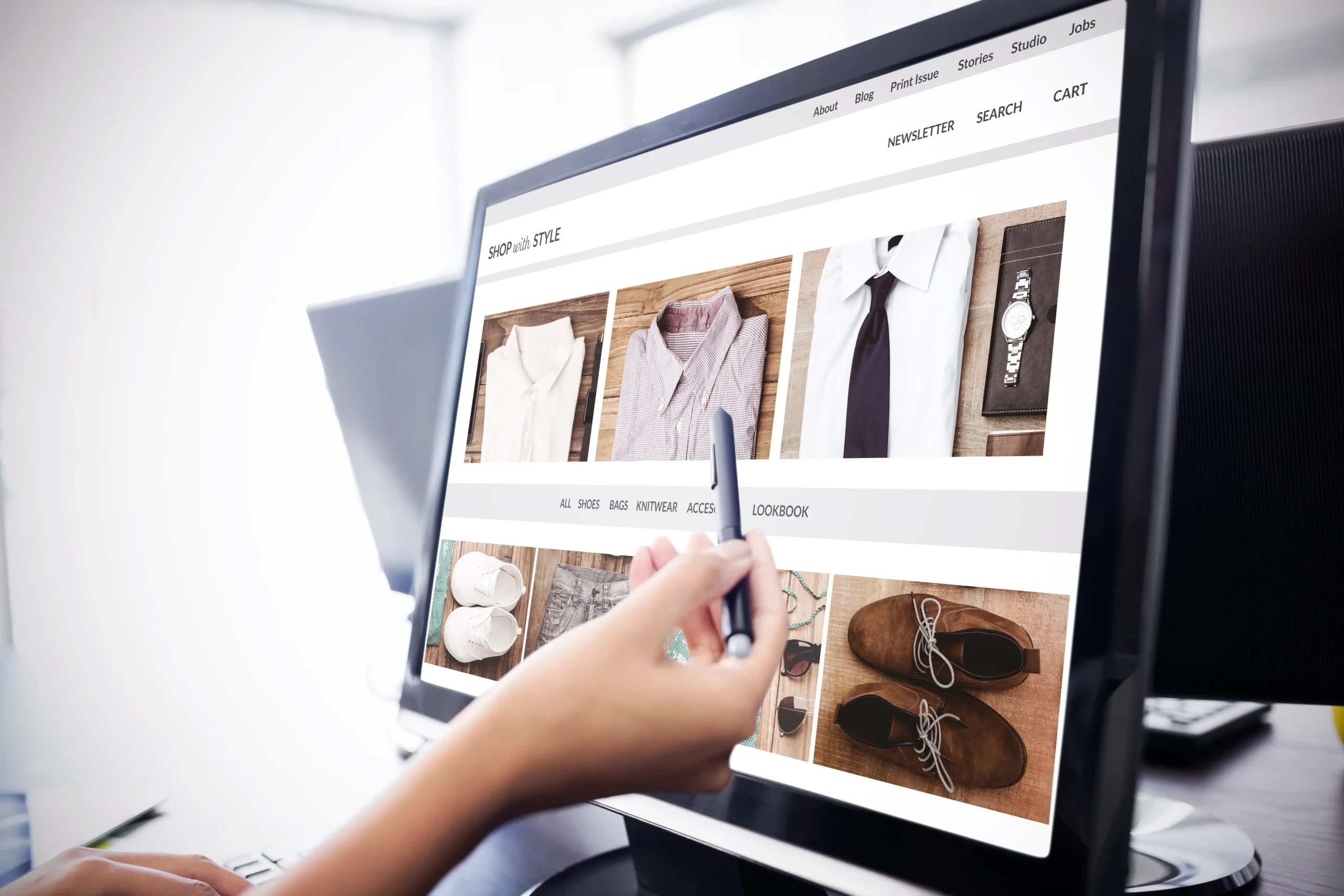成果報酬型ホームページ制作とは?失敗しない依頼方法を徹底解説

「ホームページを作りたいけれど、失敗したら費用が無駄になるのでは…」
そう考えて踏み切れない方に注目されているのが 成果報酬型のホームページ制作 です。
成果が出なければ支払いが発生しない仕組みのため、リスクを抑えて依頼できる点が大きな魅力。
しかし一方で、「成果の基準が不明確」「想定以上の費用になる」など注意すべき点もあります。
この記事では、成果報酬型ホームページ制作の仕組みからメリット・デメリット、依頼時のポイントまでを詳しく解説します。
最後には、実際に安心して依頼できるサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
応用情報処理技術者、Linux Professional、ITIL Foundation etc
第1章:成果報酬型ホームページ制作とは?
成果報酬型とは、制作会社に支払う報酬が「成果の有無」によって決まる仕組みです。
一般的な制作では契約時に数十万円の初期費用が発生しますが、成果報酬型では 集客数・問い合わせ件数・売上などの成果が出てから報酬が発生 します。
例:
-
ホームページからの問い合わせが10件を超えた時点で報酬発生
-
売上が一定額を超えた場合のみ制作費用を支払い
-
成果に応じて変動する成功報酬率
つまり「作っただけで終わるサイト」ではなく「結果につながるサイト」制作を重視したモデルです。
第2章:成果報酬型のメリットとデメリット
成果報酬型ホームページ制作は、「成果が出たときにだけ費用が発生する」という分かりやすい仕組みが大きな特徴です。従来のように契約時点でまとまった金額を支払う必要がないため、多くの中小企業や個人事業主から注目されています。ただし、すべてのケースで万能というわけではなく、仕組みを誤解して依頼すると後悔する可能性もあります。ここでは、具体的なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
成果報酬型のメリット
1. 初期費用を抑えて導入できる
通常のホームページ制作は、デザイン・システム開発・コンテンツ作成などを含めると数十万円から百万円以上の費用がかかることがあります。特に小規模事業者や新規開業者にとって、初期費用の負担は大きなハードルです。
成果報酬型であれば「成果が出るまでゼロ円」からスタートできるため、資金繰りに余裕がない企業でも導入しやすいのが最大の強みです。
2. 制作会社も成果に本気で取り組む
従来型の契約では、ホームページが完成した時点で制作会社の仕事は一区切りとなることが多く、成果が出なくても責任は依頼者側にありました。
しかし成果報酬型では、問い合わせ数や売上といった成果が出なければ報酬を得られません。結果として、制作会社は依頼者の成果を自分ごととして捉え、集客導線やSEO、コンテンツ設計に本気で取り組む傾向が強まります。
3. リスクを最小限に抑えられる
「高い制作費を払ったのに、結局集客できなかった」という失敗例は少なくありません。成果報酬型なら、こうしたリスクを最小限にできます。
実際に問い合わせや売上が発生してから費用が発生するため、費用対効果を確認しながら安心して運用できるのです。これは特に初めてホームページを依頼する方にとって大きな安心材料になります。
成果報酬型のデメリット
1. 成果の基準が不明確になりやすい
成果報酬といっても、その「成果」の定義は契約によって異なります。
例:
-
「問い合わせフォームからの送信1件ごとに◯円」
-
「商品購入1件ごとに◯%」
-
「売上が◯円を超えた場合に報酬発生」
依頼者が「問い合わせ件数」を想定していたのに、制作会社は「売上額」を基準にしていた、というような食い違いが起こるとトラブルにつながります。契約時に必ず基準を明文化しておく必要があります。
2. 長期的には費用が高くなる場合がある
最初は成果報酬で負担が軽く感じても、成果が安定して出るようになると報酬額が積み上がり、固定費型よりも高額になるケースがあります。
例えば「問い合わせ1件あたり5,000円」の契約で、月に100件の問い合わせがあれば50万円の支払いとなり、通常の制作費を大幅に超えてしまう可能性もあります。
3. 制作範囲が限定されることがある
成果に直結しにくいコンテンツ(採用ページ、企業紹介ページ、ブログ記事など)は対象外とされる場合があります。制作会社によっては「問い合わせ導線につながる部分だけ対応」といった制約を設けていることもあり、「思っていたより対応範囲が狭い」と感じる依頼者も少なくありません。
4. 成果を出すまでに時間がかかることもある
SEOや集客は短期間で結果が出るとは限りません。制作会社が最大限努力しても、検索順位が上がるまで数か月かかる場合があります。その間は報酬が発生しないため、制作会社が積極的に取り組まなくなるリスクもゼロではありません。
成果報酬型ホームページ制作は、「短期的にリスクを抑えたい」「成果が出なければ費用を払いたくない」 という方には非常に魅力的な仕組みです。
一方で、契約条件を曖昧にしたまま進めると「予想以上の支払いになった」「必要なページを作ってもらえなかった」と後悔するケースもあります。
したがって、成果報酬型を検討する際は「成果の定義」「成果に至るまでのプロセス」「長期的なコスト」をしっかり確認した上で依頼することが成功の鍵です。
第3章:成果報酬の料金体系とよくある条件
成果報酬型ホームページ制作は「成果が出てから支払う」という点でシンプルに見えますが、実際には契約内容によって料金体系が大きく異なります。ここを正しく理解せずに契約してしまうと、「思っていたより高くなった」「成果の基準が合わなかった」といったミスマッチが起こりやすくなります。ここでは、成果報酬型でよく採用される料金パターンを整理します。
問い合わせ件数ベース
もっとも多いのが「問い合わせ1件ごとに報酬を支払う」仕組みです。
-
例:問い合わせ1件あたり5,000円
-
仮に月に20件の問い合わせがあれば、10万円が報酬となります。
シンプルで分かりやすい反面、内容が薄い問い合わせ(冷やかしや営業) にも費用が発生するリスクがあります。そのため「有効な問い合わせのみ対象」と契約書に明記しておくことが大切です。
売上ベース(成果の一部還元型)
ECサイトやオンライン予約を扱う場合に採用されやすい方法です。
-
例:ホームページ経由の売上10%を成果報酬として支払う
-
月商100万円なら、10万円を報酬として支払うことになります。
売上に比例するため、依頼者と制作会社が同じゴールを目指しやすいのがメリットです。ただし売上が伸びると報酬も増えるため、長期的には固定費より高額になる可能性があります。
成果到達型(目標達成で一括報酬)
「問い合わせが月50件を超えたら」「売上が年間500万円を超えたら」など、あらかじめ決めた基準を達成した時点で報酬が発生する方式です。
-
例:売上500万円を超えたら、一括で50万円支払う
依頼者にとっては「成果が出るまではゼロ円」で安心感がある一方、ハードルが高すぎる条件を設定されると制作会社が本気で動かなくなるリスクもあるため注意が必要です。
最低料金+成果報酬のハイブリッド型
成果報酬型といっても、完全にゼロスタートではなく「最低料金」を設定するケースもあります。
-
例:月額3万円の固定費+成果に応じて追加報酬
-
依頼者は一定額を支払う必要があるものの、制作会社のモチベーションが維持されやすい
「完全成果報酬では制作会社が本気で動かないのでは」と不安な場合、このハイブリッド型は妥協点となる仕組みです。
成果報酬型の料金体系は大きく分けて
-
問い合わせ件数ベース
-
売上ベース
-
成果到達型
-
最低料金+成果報酬型
の4種類があります。どの方式を選ぶかによって費用感やリスクが大きく変わるため、契約前に「成果の基準」「支払い条件」「上限額」をしっかり確認することが重要です。
第4章:成果報酬型で依頼するときの注意点
成果報酬型ホームページ制作は魅力的な仕組みですが、「成果の定義が曖昧」「条件が不透明」といった理由でトラブルが起こりやすい契約形式でもあります。ここでは、依頼する際に必ず確認しておきたい注意点を整理します。
成果の定義を明確にしておく
「問い合わせ件数」「売上」「資料請求」「予約数」など、成果の基準は制作会社によって異なります。
-
冷やかしや営業メールも成果としてカウントされるのか
-
売上の定義は「税込か税抜か」
-
予約キャンセル分は成果に含むのか
こうした条件を曖昧にすると、後で「思っていたのと違う」と揉める原因になります。契約書に具体的に記載しておくことが必須です。
成果が出るまでの期間を想定しておく
SEOや集客は短期間で成果が出るとは限りません。半年以上かかるケースも珍しくなく、その間「報酬ゼロで頑張ってもらえるのか?」という点も確認が必要です。
-
初期は固定費を設定している制作会社
-
成果が出るまでサポートが縮小される制作会社
両者では結果に大きな差が出ます。
上限費用を確認する
成果報酬は「成果が増えるほど支払いが増える」仕組みです。例えば問い合わせ1件5,000円で、月100件の問い合わせが来た場合は50万円の支払いになります。固定費型と比べて高額にならないよう、月額や年間の上限金額を取り決めておくことが安心です。
制作範囲を把握しておく
成果報酬型では「成果に直結する部分だけを制作対象とする」場合があります。
-
問い合わせフォームや商品ページは対応
-
採用ページや会社概要ページは対象外
このように範囲が制限されるケースもあるため、依頼前に「どこまで対応してもらえるのか」を必ず確認しておきましょう。
第5章:成果を出すために依頼者が準備すべきこと
成果報酬型ホームページ制作は、制作会社にすべてを丸投げすれば成果が出るという仕組みではありません。制作会社は設計・デザイン・導線づくりの専門家ですが、事業の内容や顧客の理解は依頼者が最もよく知っています。依頼者が主体的に準備を行い、制作会社と協力することで初めて「問い合わせや売上につながるホームページ」が完成します。以下では、依頼者が事前に取り組むべき準備を、より具体的に整理します。
自社の強みとターゲットを言語化する
成果を上げるホームページには「誰に」「何を」届けたいのかという明確な軸が必要です。地域で唯一の特徴や、競合に勝るサービス内容を言語化し、ターゲット像を鮮明に描くことで、制作会社は狙いを定めた設計が可能になります。これが不十分だと、一般的で無難なサイトにとどまり、成果には結びつきにくくなります。
写真や動画を通じて事業のリアルを伝える
制作会社はデザインや導線設計のプロですが、事業の雰囲気をリアルに伝えられる素材を持っているのは依頼者自身です。商品の写真、サービス現場の様子、代表者の言葉やスタッフの笑顔などは、訪問者の信頼を得る決め手になります。こうした素材を前もって準備することが、サイトの完成度を大きく左右します。
問い合わせ対応の体制を整える
ホームページの成果は問い合わせや注文に直結しますが、それに対応できる社内の仕組みが整っていなければ顧客を取り逃がすことになります。問い合わせメールにすぐに返信するルールや、電話の受け答えを担当する人員の配置など、社内での対応体制を準備しておくことは必須です。特に成果報酬型では、問い合わせ数そのものが評価の対象になることも多いため、この準備を怠ると成果を活かせなくなります。
制作会社との協力でコンテンツを育てる
SEOや広告運用は制作会社の専門領域ですが、その中身を補うのは依頼者の役割です。ブログやお知らせの原稿、新商品やイベント情報など、現場からの情報提供があることで、サイトは生きた営業ツールへと育ちます。制作会社と依頼者が「二人三脚」でコンテンツを作ることで、集客力は飛躍的に高まります。
成果を客観的に測定する仕組みを持つ
「どれだけ成果が出ているのか」を依頼者自身も把握できるようにすることは、成果報酬型では特に重要です。アクセス解析ツールの導入や、問い合わせフォームに流入経路を記録する仕組みを組み込むことで、制作会社との成果確認がスムーズになり、費用対効果を冷静に判断できます。
成果報酬型ホームページ制作の成功は、依頼者自身の準備次第です。強みとターゲットの整理、リアルを伝える素材の準備、社内対応体制の構築、制作会社との協力体制、成果測定の仕組み。これらを整えることで、ホームページは単なる会社紹介ではなく、安定的に成果を生み続ける営業基盤へと成長します。

成果報酬型でホームページ制作を依頼するなら、まずは無料相談から
ホームページは「作ること」ではなく「成果を出すこと」が本当の目的です。
成果報酬型なら、無駄な初期投資をせずに安心して挑戦できます。
「本当に成果が出るのか不安…」
「どんな条件で依頼できるのか知りたい…」
そんな疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの事業内容に合わせた最適なホームページ制作プランを、専門家が丁寧にご提案いたします。
課題で探す